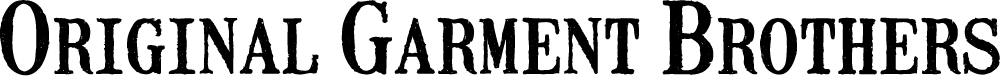「肉厚」で「柔軟」なダック生地を探す。
古くからワークウエアの定番素材として使われてきたダック生地。太めの糸を密に平織りした生地で、表面を見ると格子状に織られているのが特徴だ。
一方、我々に馴染みの深いデニム生地は綾織りのため、織り目が斜めになる。デニム生地の裏を見れば一目瞭然だ。
平織りで高密度で織られたダック生地は耐久性が高く、摩擦強度にも優れている。極限の耐久性が求められるアメリカ軍の装備にも使われるマテリアルだ。
ダック生地にも星の数ほどの種類が存在する。厚みや重さ、硬さ、着込んだ後の風合い、それぞれのダック生地に特徴がある。その中から理想のダック生地を選び出す。どんなに秀逸なデザインやディテールでも、素材のセレクトを誤ればジャケットの雰囲気は台無しとなる。
プロの知識と経験に頼る。
岡山児島へ向かう。児島は決して広いエリアではないが、ここに来れば、縫製ファクトリー、生地屋、洗い場、副資材……デニムを中心とした衣類に関わるすべての環境、モノが揃う。そして、プロフェッショナルたちに出会える。
生地屋には大量の生地サンプルが集まり、実際に触りながら、確認することができる。ラックに吊るされた大きな生地サンプルだけでなく、名刺大にカットされた生地サンプルも分厚いバインダーにストックされている。
この膨大なストックの中から、理想のダック生地に辿り着くには、いったいどれほどの日数が掛かるのか。そんな時に頼りになる存在が、テキスタイルのプロフェッショナル、鈴木氏だ。
遠慮はしない。厚みや色、手触りはもちろん、色落ち具合、重さ、柔らかさなど、思う限りのリクエストを鈴木氏に投げる。そのリクエストに基づき、続々と目の前に生地サンプルが現れる。
理想のダック生地に出会えなければ、冬用JKTのプロジェクトは成立しない。「理想の生地が無かったので、妥協してこれに……」など論外。ブラザーに対して失礼極まりない。
数時間、生地屋に居座っても理想の生地は現れない。意外と焦るものだ。ところが、その瞬間は突然やって来た。

三拍子揃った、理想のダック生地。
ダック生地は肉厚であるほどタフだが、厚過ぎると着心地を損ねる。そのため、一定の厚み以上は候補から外していた。
生地屋を訪れ、数時間後、ひと休みも兼ねて候補から外していた厚いダック生地たちを眺めていた。思った通り、硬く、バリバリ感が半端ない。ところが、一枚のダック生地の切れ端に目が留まった。
まず、色が抜群に良い。ブラウンだが、カーキが少し混ざったようなくすんだ茶褐色。思わず「この色、理想」と呟く。しかし、未洗いの生地サンプルを触ると、やはり硬い。
その下に並んだウォッシュ後の生地サンプルを触った瞬間、心臓の鼓動が一気に高まる。
これだ。柔らかい。肉厚だが、柔らかい。「厚み」「柔らかさ」そして「色」。三拍子揃ったダック生地。とうとう現れた。
この生地は絶対にいい。喜びよりも安堵。これで理想の一着が作れる。

定番には定番たる所以がある。
オリジナリティの一方的な主張や差別化は、時にプロダクトのバランスを大きく崩す。アメカジ専門誌の編集長時代に、幾度となく見てきた。
ライニングのブランケットは、このプロジェクトを立ち上げた当初から、定番を使うと決めていた。ヴィンテージワークウエアで目にするブランケット。見慣れた縞模様に、親しみや懐かしさを覚える。
ウール混のブランケットは、肌触りが良く、保温性も高い。数種類のカラーバリエーションから私が選んだのは、ダック生地との相性を考慮した、カーキ色が主体の縞模様。文句なしのセレクトだ。

骨太な6Wコーデュロイ。
襟にはダークブラウンのコーデュロイを使う。コーデュロイには「WALE」(ウェール)という単位があり、1インチ幅の畝(うね)の本数を示す。シャツには21ウェールなど「細畝」の生地が使われることが多いが、タフなダック生地に負けない存在感が必要。稀少な太畝の6Wを選んだ。
ボディに使うダック生地、ライニングのブランケット、そして襟のコーデュロイ。すべての生地が決まった。渋い一着になる。
美しい仕上がりを目指し、生地洗い。
今後、パタンナーが型紙を作成し、サンプル縫製へと進むが、その前にクリアすべき課題がある。それは、生地の縮率の違いに対して、どのように対応するか。
シャツJKTの縫製は、「OG-4」と同様、オガワが絶大な信頼を寄せる岡山児島の「アパレルナンバ」にお願いする。一流のアメカジブランドの生産を手掛け、縫製のすべてを知り尽くした難波社長と、上記の問題について協議した。
例えば「OG-4」のようなデニムJKTの場合、パタンナーはデニム生地の縮率を考慮して大きめに型紙を作成する。そして、縫製後の完成品を洗濯槽で洗い、乾燥して縮める。晴れて完成となる。
今回のシャツJKTは、ダック生地、ブランケット、コーデュロイという、縮率が異なる三種類の生地を使う。特にダック生地とブランケットは、縮率が想定と異なると仕上がりに大きく影響する。
生地メーカーは縮率データを持っているが、あくまで平均値だ。ダック生地が想定以上に縮めば、ライニングのブランケットはたるむ。逆に、ブランケットが縮み過ぎれば、ダック生地が引っ張られ、歪みが生じる。
リスクは高い。そこで、難波社長の提案もあり、今回は生地の状態で洗いと乾燥を施すことにした。「生地洗い」と呼ばれる方法で、アパレルの生産現場では決して珍しいことではない。
生地の状態で洗いと乾燥を施すため、裁断時の生地は既に縮んだ状態だ。パタンナーが縮率を考慮せず、仕上がり寸で作成した型紙を使って裁断、縫製すれば、美しいシルエット、誤差の少ないサイズが手に入る。
「生地を決める」という重要なミッションが完了し、ひとまず岡山児島を後にする。